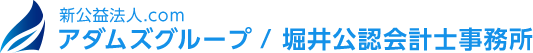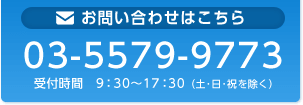任意団体の法人化とは
2022年9月に公益法人information上で公開されているFAQの一部が改正され、任意団体の法人化 及びその後の公益法人を目指す際の注意事項が記載されています。
弊社では、任意団体の学会を中心に一般社団法人に法人化する支援を多数行っています。
そこで、本記事では、FAQに記載されていない事項を解説します。
任意団体の法人化とは
任意団体(人格なき社団等)に対しては、明確な根拠法がありません。
そのため、法令の手続きに従い、任意団体を一般社団法人に「移行」するということはできません。
そこで、任意団体が一般社団法人となるためには、「一般社団法人の設立」「任意団体の解散&清算」「任意団体の財産と会員を一般社団法人に移行させる手続き」を個々に行うことになります。
これらの個々の手続きについては、法人化を目指す任意団体の状況や希望等によりいろいろなパターンが想定されます。
そのため、任意団体の状況を把握したうえで、手続きを検討する必要がありますが、実務的に行われている法人化の手続きは以下の2パターンとなります。
- 事前に少人数で一般社団法人を設立させておき、任意団体の解散と同時に財産と会員を移行させ、移行後完了後任意団体を清算するパターン
- 任意団体の総メンバーで一般社団法人を設立させ、任意団体の財産を一般社団法人に移行させた後に任意団体を解散&清算させるパターン
任意団体の法人化のメリット
任意団体を法人化することについては、単にメリットやデメリットという問題ではなく、社会的な要請等もあります。
また、どのような点をメリットと考えるかについても個人や団体の価値観や環境により変化します。
そこで、本記事では、任意団体の法人化についての一般的なメリットについて解説します。
責任の明確化
任意団体は、法人格を有しない団体であるため、規制する法律がほとんどなく、何かしら問題が発生した場合の責任問題について個々の案件ごとに判例、学説の争いが生じており、法的な不安定さがあると言えます。
例えば、任意団体に多額の債務が発生した場合に、構成員の方々の責任は、出資額を限度とする有限責任を負うのか、それとも無限責任を負うのかについても明文化された法律はないため、裁判等により個別に判断されることになります。
なお、判例は有限責任説であり、学説はケースに応じて無限責任もあり得るとする立場をとっています。
一方、任意団体が一般社団法人となった場合には、構成員(会員等)に責任はないことや理事等の役員の責任の範囲、責任の免除・限定など法律上の責任関係が明確化され、御法人の関係者の法的な安定性を確保できることになります。
財産の保有
任意団体の財産の保有は、構成員の共同所有として取り扱われます。
また、任意団体名義での登記はできないことになっておりますので不動産などの登記を必要とする財産を任意団体名義で保有することはできず、構成員全員の共同所有として登記が必要となり、手続きが非常に煩雑となります。
さらに、銀行口座については、個人名義で作成されることとなり、所有権が不安定になっているケースも存在しています。
一方、任意団体が一般社団法人となった場合には、法人名義での登記や口座開設などが可能なため、法人の財産が明確化され、煩雑な手続きも回避することが可能となります。
社会的地位の向上
任意団体は、法的に不安定であり、かつ登記等もなされないことから社会的な信頼性は低い傾向にあります。
一方、一般社団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」とします。)という根拠法もあり、法的な安定性も確保されています。
また、法人登記も行われることにより、法人としての実態について外部からも確認が可能となり、結果としてより社会的に信頼性の向上も期待されます。
任意団体の法人化による制約等
任意団体を法人化することにより、任意団体として活動していた時に出来ていたことが出来なくなることも多くあります。
これらについてデメリットと表現することは、個人や団体の価値観によるところがあります。
そのため、本記事では、任意団体の法人化についてのデメリットではなく、制約等として解説を行います。
機関設計の制約
役員の設置などの機関設計について任意団体の場合、規制する法律などがなく、自主的な運営をすることが可能です。
しかし、一般社団法人の場合には、一般法人法の定めに従い、機関設計等を行う必要があります。
理事及び監事の理事会出席義務
任意団体は、理事本人が理事会に出席しなければならないというルールはありません。
また、理事会での委任状や書面決議も可能としている任意団体が多くあります。
一方、一般社団法人の場合は、理事会について委任状や書面決議は認められていません(社員総会は委任状も書面決議も可能です)。
そのため、一般社団法人の理事は、理事会に本人が出席する必要があります。
ここで、過半数の出席がない理事会は、有効となりませんので、理事会に出席できる理事を選定する必要があります。
なお、監事については、理事会の構成員ではありませんので、出席の有無に関わらず理事会は有効となりますが、監事には理事会に出席する義務が法定されていますので、監事が欠席した場合には、当該監事の任務懈怠責任を問われる可能性があります。
理事及び監事の任期
任意団体は、理事及び監事の任期は、会則により自由に決定することが可能です。
一方、一般社団法人の場合は、理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで(短縮可能)、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで(ただし、定款で2年以内に短縮可能)となっており、一定の年数に法定されています。
社員総会の権限、理事会の権限の明確化
任意団体は、総会の権限と理事会の権限を会則により自由に決定することが可能です。
一方、一般社団法人の場合は、総会の決定事項として、理事会の権限では決定できない事項も多々あります。
例えば、理事及び監事の選任、理事及び監事の報酬額、定款の変更、解散等については、理事会の決議事項とすることはできません(理事の報酬については一部例外あり)。
決算スケジュール
任意団体は、決算のスケジュールは、自主ルールとなるため、柔軟な対応が可能となっています。
一方、一般社団法人の場合は、決算後、数箇月以内(通常3箇月以内)に総会を開催する必要があります。
また、総会の開催にあたり、原則として2週間以上前(中14日)に招集通知に決算書を添付し発送しなければなりませんが、当該決算書は、監事の監査が終わり、理事会の承認を得たものでなければなりません。
そのため、総会の開催の2週間以上前(中14日)に理事会の開催をしなければならないなど、一定のルールに従い決算のスケジュールを検討する必要があります。
まとめ
任意団体の法人化についての手続きの概要と法人化のメリットや制約等について解説を行いました。
一般社団法人の設立については、通常の設立と同じであるため、問題になることはありません。
ただし、任意団体に既存の会員がいる場合は、任意団体の制度を維持しながら一般社団法人になりたい等の要望が多くあります。
そのため、任意団体の法人化は、それらの要望を一般法人法の制度の範囲内で実現するような制度設計を検討を事前に行うことが非常に重要となります。