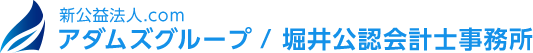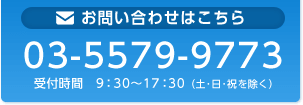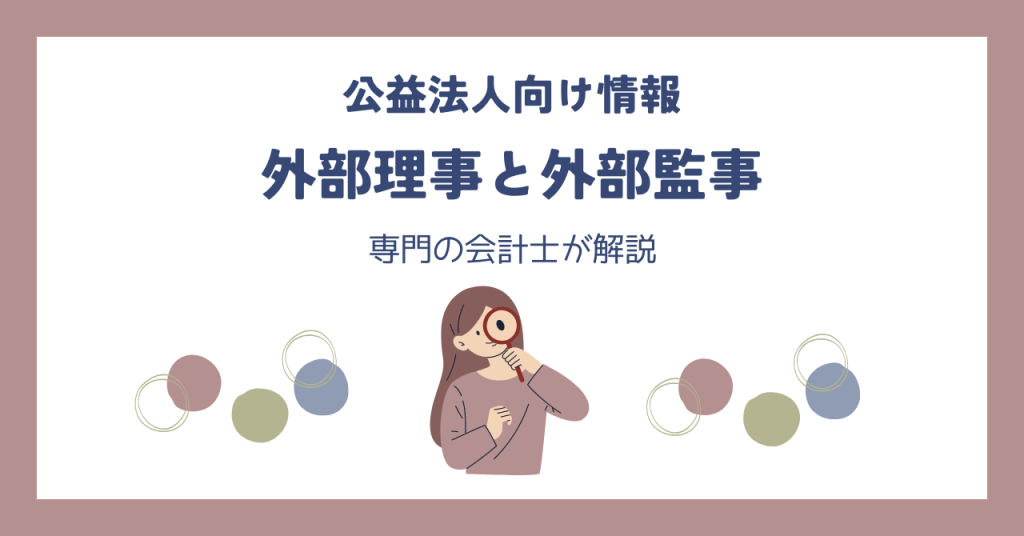
外部理事と外部監事とは
記事の対象者
本記事は、「公益社団法人」「公益財団法人」の事務局の方、2025年4月以降に公益認定を目指し、外部理事や外部監事について検討をされている方向けの記事となります。
なお、本記事内では、「公益社団法人」「公益財団法人」を総称して「公益法人」と記載し、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」を「認定法」と記載しています。
記事の概要
本記事は、外部理事及び外部監事の要件と導入方針について解説を行っています。
なお、本記事は、公益認定等ガイドライン(2024年12月改訂)を参考に作成しています。
そのため、今後の公益認定等ガイドライン等の内容が更新される可能性があることにご留意ください。
外部理事及び外部監事の要件
外部理事や外部監事については、認定法の改正により公益認定基準の1つに追加されました。
以降、外部理事及び外部監事の要件について解説します。
理事又は使用人でない者
外部理事とは
まず、外部理事は、当該公益法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人ではなく、かつ、その就任前10年間に当該公益法人又は子法人の業務執行理事又は使用人であったことがない者である必要があります。
業務執行理事とは
ここで、業務執行理事とは、代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって公益法人の業務を執行する理事として選定されたもの、当該公益法人の業務を執行したその他理事をいいます。
なお、業務執行理事のうち「当該公益法人の業務を執行したその他理事」について公益認定等ガイドラインでは、以下のように定められています。
- 対象となる理事が法人の事業に関わる業務を執行したかどうかで判断されるものであり、当該理事が行った行為が、「業務の都度又は内部規定等によって個別に委任されていたか」、「その内容は、当該理事が単独で法人の事業に係る意思決定又は意思表示を行うものであるか」、あるいは「法人内部における指揮命令権を行使するものであるか」等を踏まえ判断します。
- 例えば、理事が法人内部の委員会において委員を務め、助言や審議を行う行為は、当該理事が単独で法人の事業に係る意思決定を行う行為ではないことから、業務を執行したとはみなされません。
外部監事とは
次に、外部監事は、当該公益法人又はその子法人の理事又は使用人ではなく、かつ、その就任前10年間に当該公益法人又は子法人の理事又は使用人であったことがない者である必要があります。
なお、外部監事については、外部理事と比較して更に外部生を求められており、業務執行理事以外の理事及び理事であった者についても、外部監事となることはできません。
公益社団法人の社員でない者
次に、公益社団法人の社員は、外部理事及び外部監事となることはできません。
学会などの場合は、正会員を社員にするなど、会員制度と社員総会で議決権を行使できる社員が紐づいていることが多くあります。
このような公益法人の場合は、理事や監事を正会員の中から選定していることが多くあるため、会員以外の者から理事や監事を選任するための対応が必要となるケースが多いと想定されます。
社員が法人の場合の取り扱い
なお、公益社団法人の社員が株式会社などの法人である場合は、社員である当該法人の役員及び使用人は、外部理事及び外部監事となることができません。
代議員制度を採用している場合
代議員制度を採用している場合は、代議員以外の会員は社員に該当しません。
公益財団法人の設立者でない者
公益財団法人の設立者は、外部理事及び外部監事になることはできません。
なお、公益財団法人の設立者が株式会社などの法人である場合は、設立者である当該法人の役員及び使用人は、外部理事及び外部監事となることができません。
外部理事の適用除外基準
適用除外基準
外部理事については、事務負担等を考慮し、下記のすべての要件を満たす公益法人に対しては、適用が除外されています。
- 収益の額が3,000万円未満
- 費用及び損失の額が3,000万円未満
なお、外部監事については、適用除外の定めがなく、すべての公益法人が導入を行う必要があります。
事前の準備等の対応方針
事業年度後の計算書類等の提出にあたり、適用除外基準を超えることが判明した場合には、その時点から設置義務が生じることになります。
そのため、事前に社員総会や評議員会において当該計算書類等の承認に併せて外部理事の設置及び選任をしておくなどの対応が求められます。
突発的に基準を超えてしまった場合
突発的に収益及び費用・損失が3,000万円以上となった公益法人等に直ちに外部理事を選任することは、容易ではありません。
そのため、外部理事の設置に係る監督については、公益法人の置かれた状況の諸般の事情を考慮することになっています。
新制度施行直後の対応
外部理事の設置について、施行の際に現存する公益法人は、当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日から当該規定が適用されることとになります。
また、外部監事の設置について、施行の際に現存する公益法人は、当該公益法人の全ての監事の任期が満了する日の翌日から当該規定が適用されることとになります。
なお、急遽の外部理事の選任、定款等の改訂等を行うことができない場合には、外部理事・監事の選任に係る手続の状況や選任までの見通しなどについて行政庁から法人に説明を求めることとし、やむを得ず困難であると認められる場合には、基本的に本件に対する監督は行わないこととなっています。
理事と監事との間の特別利害関係の排除
認定法の改正に伴い、公益認定基準の1つに各理事と監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)との間で特別利害関係を有してはならないことが追加されました。
当該認定基準の追加に伴い理事と監事の親族関係についても規律が設けられたことになります。
当該基準は、外部理事や外部監事の要件とは関係ありませんが、理事と監事の親族関係も不可となったことに伴い、外部の方への理事及び監事の選定をさらに難しくする可能性があるため留意が必要となります。
なお、2025年4月1日において特別利害関係にある理事及び監事である場合であっても、当該理事及び監事の任期中に解任等を行う必要はなく、いずれかの改選期に対応すれば良いとされています。
外部理事及び外部監事の導入対応
今後、外部理事及び外部監事の導入にあたり以下のような事項に留意が必要と考えられます。
外部理事及び外部監事に対する報酬規程等の見直し
一部の公益法人では、理事及び監事の報酬を無報酬とし、その旨を定款や規程で定めているケースもあります。
ここで、条件を満たす外部の方に理事及び監事の就任を依頼するにあたり報酬が必要となることも想定されます。
そのため、当該外部役員制度導入に伴い報酬を支払が可能となるように定款や規程等の見直しの検討が必要と考えます。
理事及び監事の選定方法等の運用の見直し
一部の公益法人では、理事の退任後に監事になる横滑り人事を行っているケースもあります。上記のような運営を行っている公益法人で横滑りしている監事は、外部監事の要件を満たさないことになるため、別途外部監事を選定するための運用の見直しが必要となります。
また、公益社団法人の場合、社員(正会員など)の中から選挙で監事候補を選定するルールを設けている公益法人があります。
上記のような公益法人は、外部監事を選定するための運用の見直しが必要となるため、選挙規程等の改訂するための早期の検討が必要となります。
まとめ
本記事では、公益法人における外部理事等の導入に関する要件と、その運用に関する重要なポイントを解説しました。
公益法人の外部の方に理事又は監事に就任して頂くことは、要件に該当する方を選定するとともに、各種準備が必要になると想定されます。
そのため、特別利害関係の排除や報酬規程の見直し、横滑り人事の解消といった運営の見直しも重要な課題となります。
当該制度の導入にあたり、規程や運用の見直しについては、早期の準備が必要となります。
関連記事
- 【中期的収支均衡の概要】
- 【公益目的事業比率の概要】2025年4月以降版
- 【使途不特定財産額の保有制限】
- 【公益目的事業継続予備財産】要件等の解説
- 【公益法人の公益充実資金とは】改正情報
- 【外部理事と外部監事】公益法人向け改正情報
- 【公益法人の奨学金】公益認定等ガイドライン解説
- 【公益法人の事業内容】申請書記載方法
- 【公益法人の変更認定と変更届出】改正情報解説